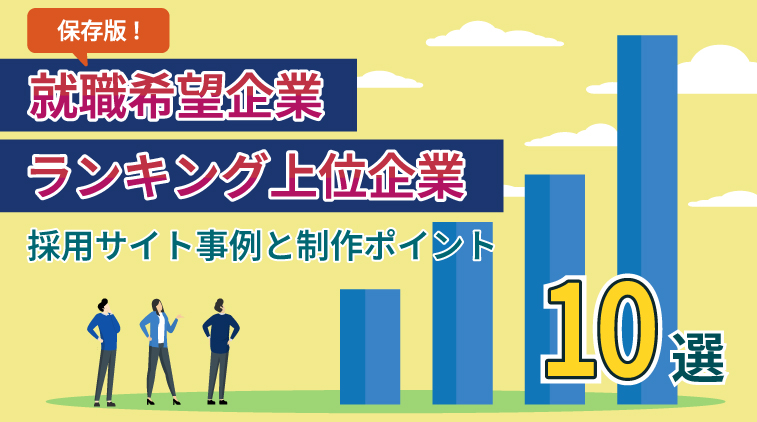ブログ > 採用サイトの「よくある質問(FAQ)」の効果的な作り方
公開日:2025.09.04 / 最終更新日:2025.09.04
採用サイトの「よくある質問(FAQ)」の効果的な作り方
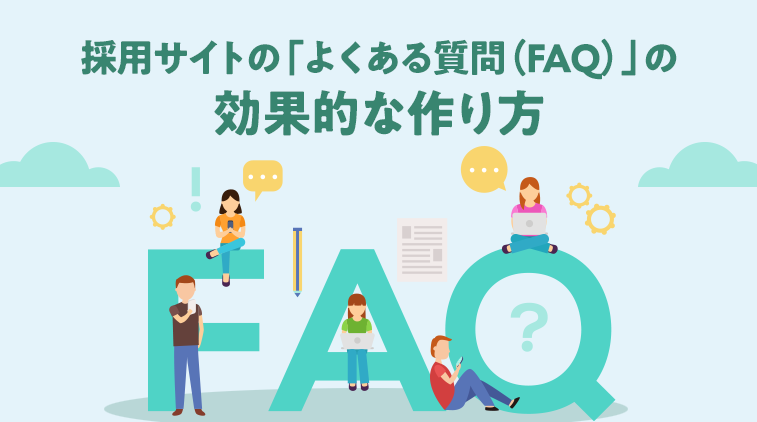
「この会社に応募したいけれど、残業時間や職場の雰囲気が分からなくて不安…」 「選考プロセスについて詳しく知りたいけれど、問い合わせするのはハードルが高い…」このような応募者の声は、多くの企業が直面している採用活動の課題です。一方で採用担当者にとっても、同じような質問への対応が業務を圧迫しているのではないでしょうか。
そんな課題を解決する強力なツールが、採用サイトの「よくある質問(FAQ)」ページです。適切に設計されたFAQページは、応募者の不安を解消し、採用担当者の負荷を軽減する、まさに一石二鳥の効果を発揮します。
この記事では、効果的なFAQページの制作方法を、目的の明確化から具体的な質問例、運用のポイントまで詳しく解説します。
目次
1.採用FAQページの目的とメリット
①応募者側のメリット
疑問解決による心理的ハードル軽減
応募を検討している求職者は、多くの不安や疑問を抱えています。給与や勤務時間、職場環境など、直接聞きにくい質問も少なくありません。FAQページがあることで、これらの疑問を気軽に解決でき、応募への心理的ハードルが大幅に下がります。
24時間いつでも情報取得可能
求職活動は平日の夜間や週末に行われることが多く、企業への問い合わせが難しいタイミングがあります。FAQページなら、応募者の都合に合わせていつでも必要な情報を得られます。
企業への理解度向上
詳細な情報提供により、応募者は企業への理解を深めることができます。これにより、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的な定着率向上にもつながります。
②企業側のメリット
採用担当者の問い合わせ対応工数削減
同じような質問への対応時間を大幅に削減できます。ある企業では、FAQ設置後に電話やメールでの問い合わせが40%減少したという事例もあります。
応募者の質向上
事前に詳しい情報を得た応募者は、企業への理解度が高く、より質の高い応募となる傾向があります。面接でもより具体的な質問が出るようになり、相互理解が深まります。
採用プロセスの効率化
基本的な情報がFAQで共有されることで、面接では本質的な話に時間を割けるようになり、採用プロセス全体の効率が向上します。
企業イメージの向上
応募者目線に立った情報提供は、企業の透明性や応募者への配慮を示し、企業ブランディングにも好影響を与えます。
③数字で見る効果
実際にFAQページを導入した企業の多くで、以下のような効果が報告されています。
・採用関連の問い合わせ件数:30~50%減少
・応募完了率:15~25%向上
・面接での質問の質:向上(より具体的で建設的な内容)
2.制作前の準備段階
効果的なFAQページを作るには、まず現状の把握と明確な方針設定が重要です。
①現状分析の重要性
既存の問い合わせ内容の分析
まずは過去6ヶ月~1年分の応募者からの問い合わせ内容を分析しましょう。メールや電話での質問、面接での質問を分類し、頻出する項目を特定します。Excelやスプレッドシートで以下の項目を整理すると効果的です。
・質問内容
・カテゴリ(勤務条件、選考プロセス、職場環境など)
・頻度
・緊急度
採用担当者へのヒアリング
現場の採用担当者から以下の点をヒアリングします。
・よく受ける質問の内容
・回答に時間がかかる質問
・説明が難しい項目
・応募者が誤解しやすいポイント
応募者アンケートの活用
可能であれば、最近の応募者や内定者にアンケートを実施し、「採用サイトで知りたかった情報」や「不安に感じた点」を直接聞いてみましょう。
②ペルソナ設定
ターゲット応募者の明確化
採用したい人物像を明確にし、その人たちが持つ疑問や不安を想定します。
・新卒者:就職活動への不安、社会人としての基本的な疑問
・中途採用者:転職理由の適合性、スキルマッチ、キャリア成長
職種別・経験年数別の考慮事項
エンジニア職では技術スタックや開発環境、営業職では営業スタイルや目標設定など、職種特有の関心事も考慮に入れます。
世代による情報収集スタイルの違い
Z世代はスマートフォンでの情報収集が中心、ミレニアル世代以上はPCでの閲覧も多いなど、世代による行動パターンの違いも意識しましょう。
3.効果的なFAQページの構成ポイント
①情報設計
カテゴリ分けの考え方
情報を整理しやすくするため、明確なカテゴリ分けが重要です。一般的には以下のような分類が効果的です。
・応募・選考について(5~8項目)
・勤務条件・待遇について(6~10項目)
・職場環境・社風について(4~6項目)
・成長・キャリアについて(3~5項目)
・その他(2〜4項目)
優先順位の付け方
問い合わせ頻度の高い項目を上位に配置し、応募判断に大きく影響する重要な項目も前半に持ってきます。理想的には、ページの上位80%で全体の問い合わせの80%をカバーできるようにします。
検索機能の必要性
質問数が20項目を超える場合は、キーワード検索機能の追加を検討しましょう。特にスマートフォンユーザーにとって、長いページをスクロールするより検索の方が効率的です。
②UI/UXの観点
見つけやすいナビゲーション配置
FAQページへのリンクは、採用サイトのメインナビゲーションやフッター、応募ボタン付近など、複数箇所に設置します。「応募前に必見!」などのキャッチコピーも効果的です。
モバイル対応の重要性
採用サイトの閲覧の60〜70%がスマートフォンからという調査結果もあります。小さな画面でも読みやすいフォントサイズ、タップしやすいボタンサイズを心がけましょう。
アコーディオン形式と一覧表示の使い分け
アコーディオン形式:質問数が多い場合、ページの見た目をすっきりさせたい場合
一覧表示:質問数が少ない場合、すべての情報を一覧できるようにしたい場合
③SEO対策
検索されやすいキーワードの盛り込み
「○○株式会社 残業時間」「○○会社 面接 服装」など、企業名と組み合わせて検索されがちなキーワードを自然に盛り込みます。
構造化データの活用
FAQ構造化データ(FAQPage スキーマ)を実装することで、Google検索結果でFAQ形式での表示が期待でき、検索流入の増加につながります。
4.質問項目の選定と分類
①基本的なカテゴリ別の重要項目
応募・選考プロセスについて
このカテゴリは応募者が最初に知りたい情報が集中するため、特に重要です。
・応募方法と必要書類
・選考フロー・期間
・面接回数・形式
・結果連絡のタイミング
・選考基準・重視するポイント
勤務条件・待遇について
転職検討者が最も関心を持つ分野です。正確で具体的な情報提供が求められます。
・給与・賞与体系
・勤務時間・残業の実態
・休日・有給取得率
・福利厚生の詳細
・転勤の有無・頻度
職場環境・社風について
「働きやすさ」を判断する重要な要素です。
・社内の雰囲気・コミュニケーション
・年齢層・男女比
・服装規定
・ランチや休憩の過ごし方
・社内イベント・交流
キャリア・成長について
特に若手層が重視する項目です。
・研修制度・教育体制
・昇進・昇格の仕組み
・キャリアパスの具体例
・他部署への異動可能性
・資格取得支援制度
②各カテゴリの重要度と優先順位
問い合わせ頻度による優先順位
過去の問い合わせデータを分析し、頻出する質問を上位に配置します。一般的には、勤務条件関連の質問が最も多く、次いで選考プロセス、職場環境の順になることが多いです。
応募判断への影響度
給与や勤務時間など、応募可否の判断に直結する項目は、問い合わせ頻度に関わらず上位に配置することを検討しましょう。
5.回答作成時の注意点
①文章作成のポイント
簡潔で分かりやすい表現
一つの回答は200〜300文字程度に収め、専門用語は避けるか分かりやすく説明を加えます。箇条書きを活用して情報を整理すると読みやすくなります。
具体的な数字・事例の活用
「働きやすい環境です」ではなく「有給取得率85%、月平均残業時間15時間」のように、具体的な数字で説明しましょう。
ポジティブな印象を与える書き方
制約やルールを説明する際も、その背景や目的を併せて説明することで、応募者に納得感を与えることができます。
②避けるべき表現
曖昧すぎる回答
「状況により異なります」「詳しくは面接でお聞きください」といった回答では、応募者の疑問解決になりません。可能な限り具体的な情報を提供しましょう。
ネガティブな印象を与える表現
「厳しい」「大変」といった表現は避け、「やりがいのある」「成長できる」などポジティブな言い換えを心がけます。
法的リスクのある記述
労働条件や待遇に関する記述は、労働基準法等の法令に抵触しないよう、人事・法務担当者による確認を必ず行いましょう。
③情報の正確性担保
関係部署との情報確認プロセス
人事、総務、法務など関連部署との連携体制を構築し、情報の正確性を担保します。特に数字データは定期的な更新が必要です。
定期的な内容見直しの仕組み
四半期に一度は内容の見直しを行い、制度変更や組織変更に合わせて情報をアップデートしましょう。
6.実際のQ&A例集
①応募・選考プロセス関連
Q: 応募から内定までどのくらいの期間がかかりますか?
A: 書類選考から最終面接まで、通常2〜3週間程度です。書類選考(1週間)→一次面接(1週間)→最終面接(1週間)→内定通知(3営業日以内)のスケジュールで進行します。ただし、応募者多数の場合や年末年始等の長期休暇を挟む場合は、多少お時間をいただく場合があります。
Q: 選考では何を重視していますか?
A: 当社では以下の3点を特に重視しています:①業務に対する意欲・熱意、②チームワークを大切にする協調性、③継続的な学習・成長への姿勢。経験やスキルも重要ですが、それ以上に「一緒に働きたい」と思える人柄を大切にしています。
Q: 未経験でも応募可能ですか?
A: はい、未経験の方も歓迎しています。入社後3ヶ月間の研修期間を設けており、業務に必要な基礎知識から実践的なスキルまで丁寧に指導します。現在活躍している社員の約6割が未経験入社です。
Q: 面接時の服装を教えてください
A: 服装の指定はありませんが、ビジネスカジュアルでお越しください。スーツでも構いませんが、普段の職場がカジュアルな環境のため、かしこまりすぎる必要はありません。大切なのは清潔感のある身だしなみです。
②勤務条件・待遇関連
Q: 残業時間の実態を教えてください
A: 2024年の実績では、月平均残業時間は12時間です。繁忙期(年度末・四半期末)は20-25時間程度になることもありますが、36協定の範囲内で適切に管理しています。また、ノー残業デーを週2回設定し、働きやすい環境づくりに努めています。
Q: リモートワークは可能ですか?
A: はい、週3日までのリモートワークが可能です。入社3ヶ月後から利用でき、現在約8割の社員が制度を活用しています。チーム会議やプロジェクト開始時など、出社が必要な日もありますが、基本的には各自の判断で働く場所を選択できます。
Q: 有給休暇の取得率はどのくらいですか?
A: 2024年の有給取得率は85%です。半期に一度、連続5日間の休暇取得を推奨する「リフレッシュ休暇制度」もあり、多くの社員がプライベートを充実させながら働いています。取得理由の申告は不要で、気軽に利用できる環境です。
Q: 昇給・賞与の仕組みを教えてください
A: 昇給は年1回(4月)、賞与は年2回(6月・12月)支給しています。人事評価制度に基づいた公正な評価により決定され、過去5年間の平均昇給率は3.2%です。賞与は会社業績と個人評価を総合的に判断し、基本給の4-6ヶ月分を支給しています。
③職場環境・社風関連
Q: 社内の雰囲気はどんな感じですか?
A: 風通しが良く、年齢や役職に関係なく気軽にコミュニケーションが取れる環境です。困ったときには先輩や上司に相談しやすく、新しいアイデアも積極的に聞いてもらえます。社員同士の仲も良く、ランチを一緒に取ったり、仕事帰りに食事をすることもよくあります。
Q: 年齢層や男女比を教えてください
A: 平均年齢は32歳、20代が35%、30代が45%、40代以上が20%という構成です。男女比は男性55%、女性45%でバランスが取れています。産休・育休からの復帰率は95%と高く、性別に関わらず長く活躍できる環境を整えています。
Q: 社内研修制度はありますか?
A: 充実した研修制度をご用意しています。新入社員研修(3ヶ月)に始まり、階層別研修、職種別専門研修、外部セミナー受講支援(年間5万円まで補助)など、継続的な成長をサポートします。eラーニングシステムも導入しており、自分のペースで学習できます。
Q: 服装規定はありますか?
A: 基本的にはビジネスカジュアルです。お客様との面談がある日はスーツ着用をお願いしていますが、普段の業務ではジーンズやスニーカーでも問題ありません。清潔感のある服装であれば、比較的自由な環境です。
④キャリア・成長関連
Q: 昇進・昇格の基準を教えてください
A: 明確な昇進基準を設けており、年2回の人事評価で判定します。評価項目は「業務成果」「行動特性」「チーム貢献」の3軸で、それぞれ具体的な評価指標があります。昇進までの目安期間は、主任クラス3-5年、管理職クラス7-10年程度ですが、成果次第では早期昇進も可能です。
Q: 他部署への異動は可能ですか?
A: 社内公募制度により、他部署への異動が可能です。年2回(4月・10月)の公募があり、希望する職種や部署に手を挙げることができます。これまでに営業から人事、エンジニアからマーケティングなど、様々な異動実績があります。
Q: スキルアップ支援制度はありますか?
A: 資格取得支援制度として、業務関連資格の受験料・教材費を全額補助しています。合格時には資格手当(月額3,000-10,000円)も支給されます。また、外部セミナーや勉強会への参加費用補助、書籍購入補助制度も充実しています。
7.よくある失敗パターンと対策
①内容面での失敗
情報が古いままになっている
制度変更や組織変更があった際の更新漏れは、応募者に誤解を与える原因となります。定期的な見直しスケジュールを設定し、関係部署との連携体制を構築しましょう。
回答が曖昧すぎて参考にならない
「詳しくは面接で」「場合によります」といった回答では、FAQページの意味がありません。可能な限り具体的な情報を提供し、どうしても個別対応が必要な場合はその理由も明記しましょう。
重要な質問が抜けている
応募者にとって重要でも、企業側が想定していない質問項目があります。定期的に新しい問い合わせ内容を分析し、FAQに反映する仕組みを作りましょう。
②デザイン・機能面での失敗
スマートフォンで見にくい
テキストが小さすぎる、ボタンが押しにくい、ページ読み込みが重いなどの問題は、応募者の離脱につながります。レスポンシブデザインは必須です。
検索機能がない・使いにくい
質問数が多い場合、目的の情報を見つけにくくなります。検索機能やフィルター機能の実装を検討しましょう。
アクセスしにくい場所に配置されている
FAQページへのリンクが分かりにくい場所にあると、せっかく作っても利用されません。メインナビゲーション、応募フォーム付近、フッターなど複数箇所に設置しましょう。
③運用面での失敗
更新されない状態が続く
制作しただけで満足し、その後の更新を怠ると情報の信頼性が低下します。更新責任者を明確にし、定期的な見直しサイクルを確立しましょう。
新しい質問への対応が遅い
時代とともに求職者の関心事も変化します。働き方改革、副業解禁、デジタルツール活用など、社会情勢に合わせた質問項目の追加が必要です。
関係部署との連携不足
人事だけでなく、総務、法務、現場マネージャーなど、各部署との連携が不十分だと情報の正確性に問題が生じます。
8.運用・改善のポイント
①継続的な改善方法
アクセス解析の活用
Google Analyticsなどでページ内でのユーザー行動を分析し、よく見られている質問や途中離脱が多い箇所を特定します。検索キーワードも分析し、求められている情報のトレンドを把握しましょう。
新しい問い合わせの分析
FAQ設置後も寄せられる問い合わせ内容を定期的に分析し、不足している情報や新しい関心事を特定します。月1回程度、問い合わせ内容を分類・集計する習慣をつけましょう。
定期的な内容見直し
四半期ごとに内容の見直しを行い、古い情報の更新や新しい質問の追加を行います。また、年1回は全体的な構成の見直しも実施しましょう。
②効果測定の方法
FAQ経由での応募数追跡
FAQページから応募フォームへの遷移数を測定し、ページの効果を数値化します。Google AnalyticsやGoogle Tag Managerを活用しましょう。
問い合わせ件数の変化
FAQ設置前後での採用関連問い合わせ件数を比較し、工数削減効果を測定します。質問の内容も分析し、FAQ で解決できている項目とできていない項目を把握しましょう。
応募者からのフィードバック収集
面接時や内定者懇談会で「採用サイトで役立った情報」について聞き、FAQページの評価を収集します。改善のヒントも得られるでしょう。
9.まとめ
採用サイトのFAQページは、応募者と企業の双方にメリットをもたらす重要なコンテンツです。成功の鍵は、応募者目線に立った情報設計と、継続的な改善にあります。
効果的なFAQページ制作のポイントを改めて整理すると、制作段階では、現状分析に基づく適切な質問選定と、分かりやすいカテゴリ分け・優先順位付けが重要です。回答作成時は具体的で正確な情報提供を心がけ、曖昧な表現は避けましょう。そして何より大切なのは、制作後の継続的な運用と改善です。
①次のステップ
FAQページの制作を検討されている場合は、以下のステップで進めることをお勧めします。
1)現状分析:過去の問い合わせ内容の洗い出し
2)社内体制整備:更新担当者の決定、関係部署との連携体制構築
3)コンテンツ制作:質問項目の選定と回答作成
4)デザイン・実装:ユーザビリティを重視したページ設計
5)運用開始:効果測定と継続的改善
必要に応じて、Web制作会社や採用コンサルタントなど外部リソースの活用も検討しましょう。
②制作時のチェックリスト
コンテンツ面
・問い合わせ頻度の高い質問を網羅している
・各回答が具体的で分かりやすい(200〜300文字程度)
・法的に問題のない表現になっている
・ポジティブな印象を与える内容になっている
・関係部署による事実確認が完了している
デザイン・機能面
・スマートフォンで見やすいデザインになっている
・目的の情報を見つけやすい構成になっている
・検索機能(質問数が多い場合)を実装している
・FAQページへのアクセスが分かりやすい
・ページ読み込み速度が適切である
運用体制
・更新責任者が明確になっている
・定期的な見直しスケジュールが設定されている
・効果測定の方法が決まっている
・新しい質問への対応フローが整備されている
採用活動の成功に向けて、応募者に寄り添った「よくある質問」ページを制作し、継続的に改善していきましょう。

執筆者:株式会社ゴマシオカンパニー 代表取締役 山崎準也
ゴマシオカンパニーは、採用広報支援を目的としたクリエイティブを得意とする企画制作オフィスです。この分野で20年以上実績を積み上げてきた代表を中心に、様々な分野のクリエイティブを得意とするスタッフが、日々アイデアを出し合い、お客さまの採用課題解決に尽力しています。
人気の記事
採用LP(ランディングページ)事例9選|成功のポイントと制作のコツを徹底解説
2025/09/10
建設会社の採用サイト事例15選|人手不足を解消する応募導線設計
2025/07/04
2025/01/31
2025/04/25
2025/02/03